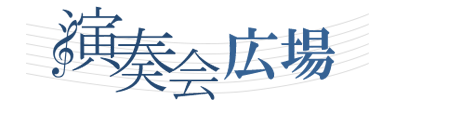個性的な作曲家がいっぱい
作曲家も同じ人間
ベートーヴェン、モーツァルト、ブラームス…いわゆるクラシックの作曲家について、
通常私たちが抱くイメージは、まず「複雑な音符をあやつる並ならぬ人」「天才」「私たちと
は違う特別な人種」である。そんな人間が書いた作品は、だから大抵が立派なもの。聴きな
じめないとしたら、それは凡人である私たちに問題がある、というふうに考えがちである。
一年、二年後にも聴かれる作品を残したという点で、それは確かにその通りなの
であろうが、しかし。偉大な”とか。天才”を過度に意識しすぎると、作曲家たちを神格化
してしまって、かえってその人間像を見失ってしまう気がしないでもない。作品のすばらし
さを味わうには、実は彼らも私たちと同じ人間だった。たまたま生まれた時代や国が違った
だけ。泣きもすれば笑いもし、恋もすれば苦労もした普通の人間の一人。ただ音楽的才能だ
けが私たちと違ったにすぎない。ぞんな人間が悩んだり苦しんだりしながら作曲したのだと考えたほうが、より身近で冷静に聴けるのではなかろうか。
実際、人間としての作曲家に目を向けてみると、実にさまざま。現代の私たちと大して変
らない、笑ってしまうような行動・生き方をした人、苦労した人、遊びをした人、恋愛や結
婚に失敗をした人、無残な死に方をした人などをいくらでも見つけることができる。作品も
いいけれど、ときにはそういう作曲家たちの人間像にスポットをあて、彼らの世界がどう
なっているのかを探るのも、クラシックと親しむための有効な手段であり、楽しみである。
この章では、そのさわり。特に個性的な生き方やエピソードで知られる何人かについて、
断片的ながらご紹介してみようと思う。いずれも有名な作曲家ばかりだが、「クラシックの
世界には、こんな人がいるのか」と知っていただくだけでなく、人間臭いそのエピソードか
ら、「彼らの世界も、私たちのそれと同じ。そんな中から作品も生まれたのだ」と、想像し
ていただくとよいと思う。親しみにくかった曲にももしかして急に親近感がわく、というこ
とが充分あり得る筈であるから。
ピアノが弾けなかった作曲家
作曲家たちは、どんなふうにして曲を書くのだろうかといえば、大抵の人が想像するの
は、ピアノに向っている彼らの姿である。五線紙を前に、少しずつ考えては鍵盤に手をやっ
て音を出す。ポツンポツンと音を確かめては、その都度書き込んでいるそんな様子がまず浮90
かぶが、当然ピアノが弾け、その腕前もかなりのものと思うに違いない。とりわけ現在のよ
うに作曲と演奏とが分業になっていなかった十九世紀までの作曲家については、その感が強
いだろ。
ところが、である。実はピアノが弾けなかった大作曲家というのもいるのである。その一
人は、「幻想交響曲」で世界的なあのE・ベルリオーズ(一八三~一八六九、フランス)
である。
フランス束南部の田舎町ラーコートーサンタンドレに生まれた彼は、父親が医者だったせ
いもあって幼い頃にはピアノなどにはまったく無縁。楽器といえば、父親の机の引出しに
あったフラジオレット(フルートの一種)ぐらいしかなかったという。やがてその音楽的才
能に気づいた父親が専門の教師につけさせた時も、マスターしたのはフルート、ギター、ド
ラムなど。パリヘ出て作曲家として成功してからも、だからピアノは和音を確かめる程度に
しか使わず、生涯にわたって彼はピアノ演奏とは無縁に終わったと伝えられている。
しかしその分、彼の頭の中にはいつも、大オーケストラの色彩的な響きが鳴りわたってい
た。オーケストラの使い方では多くの作曲家たちが影響を受けることになる、あの「幻想交
響曲」などの名作はほとんど、そうした頭の中から生み出されたものなのである。もう一人は、オペラの大家R・ワーグナー(一八一二~一八八三、ドイツ)。といっても
彼の場合はまったく演奏できないのではなく、自己流の勉強により自己流には弾いたらし
い。ライプツイヒ生まれの彼の場合は、生まれて間もなく父親に死なれ、再婚した母親の相
手が俳優だったことから、芝居とピアノに興味をもったという。後の彼を考えると、何やら
象徴的なスタートである。
その父親がウェーバーと親しかったことで「魔弾の射手」が音楽開眼となり、全曲を丸暗
記したり、自己流にピアノに移しかえたりしたのが一一歳頃。才能ありと認められて専門の
教師に師事することになったものの、自己流による勝手な癖がついてしまっていて、元へ戻
れない。嫌気がさした彼は、ここで演奏することをまったく諦めてしまうのである。作曲の
ほうは順調に進んだものの、ピアノは自己流のまま、ついに正式に演奏することはできな
かったという。
意外な感じがするのは、バロック時代の巨匠G・P・テレマン(一六八一~一七六七、ド
イツ)である。バッハ、ヘンデルと同時代に活躍し、当時の人気はナンバー・ワンだったと
いわれる作曲家。作品の数が多いことでも、古今の第一位。ら二人の作品を合わせて
もそれ以上だったといわれる数千曲。オペラ、オラトリオから器楽、管弦楽曲、声楽曲ま
で、ともかく驚くほど精力的に作曲を行なった人として知られているが、実は作曲も演奏も、すべて独学。自己流だったといわれている。チェンバロ(ピアノの前身にあたる)は、面倒と感じてやめてしまったのだとか。しかし数多
い彼のチェンバロ曲から、そんな事情を想像するのはまったく不可能である。作曲家たるも
の、必ずしも演奏できなくてもよいのかもしれない。
モーツァルトは人生の垢を旅に費やした
旅は見聞を広げる可愛い子には旅をさせよなんて言葉があるが、型にはまった日
常からの脱出である。旅は、確かにいろいろな面で私たちを刺激し、成長を促してくれる
点で魅力が大きい。しかし、だからといって終始旅に出ている。あちこちと渡り歩くことの
ほうが多いとしたら、これはジプシーやヒッピーと同じ。若いうちはいいとしても、年令を
とってからは困ることもあるのではなかろうか。
そんな放浪に似た旅を、何と六歳の頃のまだ肉体的にも未熟な頃から二五歳の青年期ま
で、延々一年以上にもわたって続けた作曲家。もしかするとそれがもとで早死したのかも
しれない、といわれているのは、ご存知オーストリアの作曲家ヴォルフガングーアマデウス
ーモーツァルト(一七五六~一七九一)である。
作曲家の旅好きは特に隕ったわけではなく、メンデルスゾーンやリスト、ワーグナー、サンーサーンスらも同じ。あちこちと旅に出てはその都度名曲を生み出しているが、それにしても六歳頃からずっとというのは極端である。現在のようにあれこれと交通機関が発達して
いたのならともかく、当時の旅というのはほとんど馬車である。道路事情も悪かった筈で、
ガタゴトと尻を痛めながらの旅が、幼いモーツァルトの身体にどれほどの影響を与えたか。
これは想像するだけで、胸が痛む。
ちなみに彼の旅というのを概観してみると、最初が一七六二年一月から三週間ほどのミュ
ンヘン行き。選帝侯マクシミリアン三世の前でピアノ演奏をして褒められたのがきっかけと
なり、うれしくなった父親が以後あちこちと連れ回すことになるのである。同じ年の九月か
らは三ヵ月半ほどウィーンへ行く。この時には女帝マリアーテレジアにキスしてもらった
り、転んだのを助け起こしてくれた皇女マリア(のちのマリー・アントワネット)に「大き
くなったら、結婚してあげる」といったりする。一七六三年(七歳)六月からは、約三年半
をかけてパリ、ロンドン、アムステルダムへ。このときには最初の交響曲を書く一方、チフ
スにかかったりする。一七六七年九月から一年四ヵ月ほどは、一家でウィーンへ。このとき
にも天然痘にかかって散々な目にあう。そして一七六九年から一七七三年三月にかけては、
三回に分けてのイタリアへの旅。バチカンのシスティナ礼拝堂で、門外不出のアレグリ作曲
「ミゼレーレ」を暗記し、後で正確に書き直して人々を驚かせたのは、このときである。一七七三年から七五年にはウィーン、ミュンヘン。二一歳の一七七七年九月には、母親と
マンハイム、パリヘ。しかしここで翌年の七月に母親が急死。同じ頃プロポーズした女性
(のちに妻となるコンスタンツェの姉アロイジア)にも振られて、失意のモーツァルト。一
七八年一一月に再びミュンヘンへ旅立つが、ここで日頃からしっくりいかなかったザルツ
ブルクの大司教にウィーンに呼びつけられ、喧嘩別れとなって遂に独立(二五歳)すること
になるのである。
旅の合計期間は、一年とニカ月。三五歳の生涯からすると、人生の三分の一を旅に費や
した。いや、もの心ついてからは、ほとんどが旅の中にあった。旅そのものが人生だった、
といってよいだろう。こんな作曲家もいるのである。
聴覚を失った作曲家
視覚・聴覚・触覚・味覚・臭覚などの感覚は、それを失ったときのことを考えると、どれ
だけ不便で困ることか、いや、苦痛に悩まされることか。想像するだけで、胸が痛むもので
ある。ましてや、それが職業に必要な道具・武器になっているような場合-画家にとって
の視覚、音楽家にとっての聴覚のようなには、これはもう悲惨としかいいようがない。
そんな状態に陥ったときの彼らは、一体どんな気持ちで仕事を考えるのだろうかと暗い気分になってしまうが、それにしても音楽の世界にそんな人がいたのだろうかというと、実はい
るのである。
その代表は、何といってもあのルードヴィッヒーヴァン・ベートーヴェン(一七七~一
八二七、ドイツ)である。愛らしいピアノ曲「エリーゼのために」や、重厚壮大な「英雄」
交響曲、幻想的な「月光」ソナタなどで知られる古典派時代の大作曲家である。耳に異常を
感じるようになったのは、二六歳頃。独立しウィーンへ出て四年後のことである。
しかし売出したばかりの彼にとって、それを知られることは、ライバルたちに足を引っぱ
られること。知られる前に治してしまおうと決意した彼は、ひそかに冷水浴やら温水浴、強
壮剤、果実油などによるさまざまな治療を試みる。しかし結果的にはかえって悪化させてし
まい、独自に作らせた補聴管などを使ったりした末に、一八一五年からはまったく聴こえな
くなった不便さから、筆談帖(相手の言葉を書いてもらい、それを見て口で答える)という
のを持ち歩くことになったのであった。
耳疾の原因については、当時流行していた梅毒によるもの、耳硬化症、内耳疾患、幼い頃
のチフスとその後の胃腸病・肝障害などの合併による、などいろいろな説があるものの、こ
れといった確証はない。おそらくはそれらのいくつかの合併症と、ベートーーヴェン自身によ
るいじり過ぎ、無茶な生活などが拍車をかけたのではないか、と専門家たちには見られている。しかし、実はベートーヴェンの傑作の大半は、この耳が悪くなってからの作曲なのであ
る。不自由な聴覚と戦いながら厳しい競争社会を生きぬいた彼の努力を思うと、その不屈さ
には頭が下がる思いである。
もう一人は、「モルダウ」という交響詩で親しまれるベドルジヒースメタナ(一八二四~
一八八四、チェコ)である。彼の場合は五歳のときであるから、ベートーヴェンよりは
ずっと年令をとってから。すでにオペラ「売られた花嫁」ほかいくつかの作品によって国民
的な作曲家にはなっていたが、「モルダウ」を含む連作交響詩「わが祖国」を書き始めた時
期のことで、「モルダウ」はまったく聞こえない暗黒の中での作曲。以後そうした状況の中
でオペラを四作も書くが、最後は脳障害を併発して躁暴状態に。ついには一八八四年四月、
精神病院に収容されてそのまゝ回復することなく狂死した。ドヴォルザークらに先立つ、
チェコ国民音楽の先駆者といわれる作曲家である。
そのほか、歌曲の分野で独特の個性を発揮したロベルトーフランツ(一八一五~一八九
二、ドイツ)もベートーヴェンと同じ年頃から異常をきたし、五三歳で聴覚を完全喪失。J
・シベリウス(一八六五~一九五七、フィンランド)やM・ファリャ(一八七六~一九四
六、スペイン)も、一時期あるいは最晩年に聴覚を失っている。こういう作曲家は、よく探
すと他にもまだいるかもしれない。なお、以上の人だちとは反対に、難聴に悩まされ、あれこれと転職を重ねているうちに三五歳頃から聴こえるようになり、それから作曲家になったという変り種もい
る。フランスのポールーデュパン(一八六五~一九四九)だが、一般にはほとんど知られて
いないだろう。オペラ「マルセル」のほか、室内楽曲、ピアノーソナタなどを書いたと記録
されている。
他人の名を借りて作品を発表した作曲家
芸名”とかンネームというのがある。世の中でうまくやっていくためにつけられ
る本名とは別の名前で、それらしい印象やインパクトを盛り込むのがミソ。「江戸川乱歩」
や「美空ひばり」など、いろいろな名前が浮かんでくる。
実はクラシックの世界にもそういう例はいくつかあって、例えば出身地の名前がそのまま
人名となって広まってしまったオッフェンバック(フランスのオペレッタの作曲家。生まれ
はドイツのオッフェンバックーアムーマイン)や、イタリア風にした方が仕事上有利だと改
名したG・P・マルティーニ(「愛の喜び」という歌曲で有名なドイツの作曲家。本名はJ
・P・A・シュヴァルツェンドルフ)らのケースは、その代表といってよいだろう。
ところがもう一人、このペンーネームに実在した古い時代の複数の作曲家の名前をつけた、そして彼らの名によって、自分の作品を発表しつづけた、約四年間にわたってと
いう、何とも図々しい、あるいは大胆な作曲家がいるといったら、誰のことかわかるであろ
うか。それはオーストリア出身のヴァイオリェストで、作曲家としても知られるフリッツー
クライスラー(一八七五~一九六二)なのである。
演奏家としての彼は、一九二三年に来日したこともあるから、古くからの音
楽ファンの中には実演を聴いた人もいるかもしれないが、超人的なテクニックに加えて上品
で甘い音色をもった。ウィーン風”のスタイルにより、世界的に人気のあったヴァイオリニ
ストの一人。しかしまた一般のファンにとっては、「愛の喜び」「愛の悲しみ」「ウィーン奇
想曲」「美しきロスマリン」などの小品を書いた作曲家として、知らぬ人がいないほど有名
である。
彼は、六歳の誕生日を迎えたある日、ニューヨークータイムズの音楽担当批評家オリン
ーダウンズに追求されて、とんでもないことを告白した。「私がこれまでに演奏してきた古
い時代のヴァイオリン曲というのは、実は皆、自分で作曲したものだ」というのである。さ
あ、大変音楽界では、「よくぞ驅した」「サギだ」と賛否入り乱れる大騒ぎになった。
というのは、彼はそれらの作品のことを、「教会などで発見した古い時代の埋もれた作品。
自分は単なる紹介者だ」として演奏してきたからである。ときには数曲を並べて、一曲だけにクライスラー作曲と記したため、批評家たちは「なかなかいい曲。しかしクライスラーの曲だけは、数段おちる」などと批評していたから、これ
によって面目まるつぶれとなってしまったわけである。
結局この騒ぎの結末はどうなったかというと、偽称した作曲家の曲について、「~の様式
による」という前置きをつけることで結着がついた(したがって、どれが該当曲だったか
は、曲名を見るとわかる)。しかしまあ、普通なら埋もれた曲に自分の名前をつけて発表す
るのが当り前のところを、その逆をいったこの行為。一体なぜだったのかというと、大曲は
やりたくてもカネがかかり、小曲には適当な曲がそれほどない。いっそ自分で、と作曲した
が、音楽界ではまだ若輩。生意気だと思われるのがいやで名前を借りたのだ、そうである。
ギャンブル好きな作曲家
ギャンブルというと、身近なところでは競馬や競輪、競艇、宝くじなどが主なところ。ど
ちらかといえば、庶民の遊びといったイメージがある。外国でもトランプやビリアートほか
いろいろな賭けごとがあるらしいが、それにしてもお堅い作品を書くクラシックの作曲家と
ギャンブルとは、私たちのイメージとして結びつきにくい。
ところが、彼らも同じ人間である。実際にギャンブルが大好き。音楽に負けないくらいの
めり込んでしまったという人も、いなくはないのである。その代表ともいうべき一人は、
ヴァイオリンの鬼才として歴史に名高い、パガニーニ(一七八二~一八四○、イタ
リア)である。
独学に近い練習によって身につけた超人的技巧により、一代からプロのヴァイオリュス
トとして名声を博した彼は、一七歳の頃にすでに大人顔負けの高収入を得ていたという。し
かし不相応の大金は、パガニーニに美食、酒、女、ギャンブルの味を覚えさせたようであっ
た。例えばギャンブルに関しては、こんな話が残されているのである。
あるとき、演奏会の直前にやったギャンブルに負けた彼は、愛用していたヴァイオリンを
取られてステージに立てなくなってしまった。しかしその才能に惚れ込んでいた一人の蒐集
家が「キャノン」と呼ばれる名器を彼に贈ってくれたお蔭で、危うくセーフ。ところがその
後、またまた負けてこの名器も取られそうになった。しかし「よ~し、最後にもう一番」
とやった勝負に勝って、危うく取られずにすんだ、というのである。ほかにも、死の三年前
にはパリにカジノをつくるという話に乗せられて出資金をだましとられ、法律上の責任者と
して責められたあげく、パリを逃げ出して各地を転々とした、という話も残されている。ま
あ、よほどギャンブル好きだったのであろう。パガニ一二ほどではないが、やはりギャンブル好きだったのはチャイコフスキー、リヒャルトーシュトラウス、ヴェルディらである。ともに健康的な遊びの域におさまっていたよう
で、いずれもトランプ。「スカート」というゲームが好きだったR・シュトラウスは、歌劇「インテルメッツォ」
(一九二三年作曲。自らの家庭のようすを描いた作品)の中に、これに興じる場面を挿入
し、チャイコフスキーもカードをめぐるドラマティックな歌劇「スペードの女王」(一八九
年)を書いている。
真相は不明だが、やはり好きだったのではないかといわれるのは、モーツァルトである。
というのは、よくいわれるウィーン時代晩年の彼の困窮ぶりが何からくるのか。夫婦そろっ
ての浪費癖によるもののほか、もしかしたらモーツァルトがカジノに出入りして負け続けた
ことも、大いに関係している、と主張する研究家がいるからである。彼によればモーツァルトの当時の収入は、減っていたとはいえ決して低いものではなく、むしろ支出に問題があった。それこそギャンブルによるものに違い
ないというのである。当時のヨーロッパでは各種のギャンブルが日常的な娯楽となっていた
から、この推測は当っていたかもしれず、モーツァルト以外にもそれを楽しんでいた作曲家
は多分いるに違いない。
悪妻をもらった作曲家
私たちの周囲でも時折耳にする。悪妻”。どういう妻をそういうのか定義するのは難
しいけれど、幸せな家庭を夢見て結婚した筈の相手が、実際にはとんでもない人だった。
思っていたのとは正反対の人だったというような場合などは、悪妻といってよいに違い
ない(もっとも、それは夫の側にも問題があるのかもしれないが)。
音楽史をひもとくと、この悪妻をもらったことで有名な作曲家―というのが、何人かい
る。例えば、フランツーヨーゼフー(イドン(一七三二~一八九、オーストリア)、ピョー
トルーチャイコフスキー(一八四~一八九三、ロシア)、W・A・モーツァルト(一七五
六~一七九一、オーストリア)らである。
とりわけ有名な(イドンの場合は、こうだ。交響曲や弦楽四重奏曲の基礎を固めたことで
知られる彼は、ボヘミアの貴族モルツイン伯の宮廷楽長をしていた二八歳の時に結婚したの
だったが、相手はかつら屋の二人娘の姉マリアーアンナーアロイジアという女性である。当
初は妹の方に恋したのだったが、プロポーズ直前に彼女は修道院へ。がっかりしているとこ
ろに姉をすすめられて、よく考えずに結婚してしまったのである。
ところが彼女は、顔のまずさはともかく、怒りっぽくてやきもちやき。家事もできないうえに、夫の職業にもまったく無関心。せっかく書きあげた楽譜を平気で包み紙に使ってしまったり、髪のセットに丸めてしまう。結婚できれば相手などはだれでもよい、といった調子の自分勝手な女性であった。
当然その仲はうまくいかなかった筈だが、結婚翌年に名門エステル(ツイ家の副楽長に
なったこともあって表面上は別れず、その代りに宮廷楽団で知り合った若いソプラノ歌手ル
イジアーポルツェリといい仲になった。そして一八年に妻が亡くなるとルイジアに対
し、他の女性と結婚しないこと。年金を払うことなどの念書を書いて、結婚はしなかったも
のの、それを誠実に実行したのであった。
チャイコフスキーとモーツァルトの場合は、一般にいわれてきた悪妻説とはちょっとニュ
アンスが違う。チャイコフスキーが結婚したのは一八七七年、三七歳の時だが、これはモス
クワ音楽院教授時代の教え子アントユーナーミリューコヴァ(二八歳)から一方的に求愛さ
れて、半ば同情から一緒になったといわれるもの。しかし彼女はただ激情的なだけで知性が
なく、神経質なチャイコフスキーとはすぐに合わないことが明らかとなり、ノイローゼに
なった彼は自殺をしようと冬のモスクワ川に入水したりする。結局、別れたのだったが、一
説によるとチャイコフスキーには同性愛の趣味があり、結婚はそれを隠すためだったともい
われているのである。離婚後のミリューコヴァは悲惨で、精神的に異常をきたした彼女は、やがて精神病院に収容されて一人淋しく亡くなったのであった。
一方、モーツァルトの妻コンスタンツェも、従来は悪妻とされてきた。それは何にでも金
を使ってしまう浪費癖や、家計のやりくりが下手で、浮気っぽいこと。加えてモーツァルト
の死後、その埋葬にも立ち会わず、一七年後になってようやく墓参りに行った、という理由
によるが、浪費癖はモーツァルトも同じで、二人の仲も決して悪くはなかった。そんな妻を
モーツァルトは最後まで愛していたらしいことからも、必ずしも悪妻とはいえないようであ
る。モーツァルトもまた(イドンと同じに、二人姉妹の一人(「魔弾の射手」で有名なウェ
ーバーの親戚筋)であるコンスタンツェと結婚(一七八二年)したのだったが、当初は姉の
アロイジアに恋し、ふられた結果、妹に切替えたのだという。
女流作曲家
クラシックに興味をもつようになると、誰もがどこかで気がつくのは、作曲家のほとんど
が男性だということである。演奏などでは女性も多いから、当然作曲の世界にも居た筈だと
思われるのに、さてだれがいるだろうかと考えると、すぐには思い浮かばない。これは一体
どうしたのかとふしぎに思う人も多いだろう。
なるほど、現在はともかく音楽史全体を通してみると、ベートーヴェンやモーツァルトのような目立った作曲家がいないのは確かである。それは社会的に女性に向いた職業と考えら1
れていなかった事情もあるであろうし、いることはいても相対的に少ないことから傑出した
人が出にくかったこともあるかもしれない。しかし、である。よく考えると私たちに親しい
女流作曲家も、実はいるのである。どんな人がいるか、ここでは主な人たちをまとめてみる
ことにしよう。
まずだれもが知っていそうなのは、愛らしいピアノ曲「乙女の祈り」を書いたテクラーバ
ダジェフスカ(一八三四~一八六一、ポーランド)である。ワルシャワに生まれ、わずか二
七歳で亡くなった彼女については詳しい経歴がわかっていないが、似たような小品を三五曲
ぐらい作曲したらしい。たまたまその一つ「乙女の祈り」がパリの音楽雑誌「レビュー・エ
ーガゼットーミュジカーレ」の付録として載せられたことから人気を得、たちまちに世界的
に知られるようになったのである。一八歳の時の作品だそうである。
モーツァルトと同時代のピアニスト兼作曲家、マリアーパラディス(一七五九~一八二
四、オーストリア)は、ヴァイオリンの小品「シチリア舞曲」によって知られている。モー
ツァルトとも親交があり、実際にピアノ協奏曲第一八番を献呈されてもいる彼女は、若いと
きに失明したにもかかわらず努力して成功し、後には音楽学校を設立したほどの人格者。S
・ドウシキンの編曲によって人気の出た「シチリア舞曲」の原曲はピアノ曲だが、心に浸みる実に美しい曲である。
フランスには、セシルーシヤミナード(一八五七~一九四四)、ナディアーブーランジェ
(一八八七~一九七九)、リリー・ブーランジェ(一八九三~一九一八)、ジェルメーヌータ
イユフェル(一八九二~一九八三)の四人がいる。シヤミナードはヴァイオリン曲「スペイ
ンのセレナード」で知られ、ブーランジェ姉妹の姉ナディアは教育者として、妹リリーは
ヴァイオリン用「夜想曲」と女性初のローマ大賞受賞者として、タイユフェルは「フランス
六人組」の一人として、それぞれに有名である。
ドイツでは、ロベルトーシューマンと結婚したクララーヴィーク(一八一九~一八九六)
と、フェリックスーメンデルスソーンの四歳年上の姉ファニー・メンデルスゾーン(一八
五~一八四七)の二人が見逃せない。共にこれといって知られる名曲はないのだが、例えば
クララの「ピアノ協奏曲」と「ピアノ三重奏曲」、ファニーの「ピアノーソナタ」などを聴
くと、その美しさや豊かな曲想は、シューマン、メンデルスゾーンに劣らぬ魅力的なもの
で、なぜ埋もれているのか、ふしぎなほどである。
酒を愛した作曲家
愛好家にいわせると百薬の長であり、血行や頭の働きを滑らかにするのが酒。。真実は酒の中にある。真実をいう気持を持つためには、酔っていなければならない(リュツケルト)なんて言葉もあるように、小説家や音楽家、画家など、いわゆる創作活動をする
人と酒との関係は、意外にも深いようである。音楽史をひもといても、特に酒好きとして知
られた作曲家が何人か見つかるからである。
例えばその筆頭は、クリストフーグルック(一七一四~一七八七、ドイツ)と、モデスト
ームソルグスキー(一八三九~一八八一、ロシア)だろう。共にその酒で命をおとしている
のである。オペラ「オルフェオとエウリディーチェ」で知られるグルックは、表向きは脳溢
血で死んだことになっているが、実際にはブランデーによるアルコール中毒死である。とい
うのは、日頃からブランデー愛好家であった彼。晩年に軽い卒中で倒れて以来、医者からこ
れを禁じられ、妻からも厳しく見張られていた。
ところがその妻が何かの用事で外出した折、家中を探して一本のブランデーを見つけてし
まったのである。しめたとばかりに飲み始めたのはよかったが、禁酒によってアルコー
ルに対する免疫がなくなっていたのであろう。あっという間にひっくり返ると、そのまま息
を引き取ってしまった。
「展覧会の絵」でおなじみのムソルグスキーも、まったく同じ。ロシア人であるから多分
ウオッカだったと思われるが、若い頃からの愛飲に母親の死(彼二六歳の時)が拍車をかけ、四歳を過ぎる頃には、完全なアルコール中毒者に、一八八一年、演奏中に倒れた彼
は、急拠病院に収容されて、禁酒の療養を強いられることになった。ところがまじめな養生
によって回復したかに見えた誕生日前のある日。付添いの一人が誕生日の祝いのつもりで差
し入れたのが一本のブランデー。喜んで飲んだムソルグスキーはたちまちおかしくなり、奇
しくも誕生日の朝に亡くなってしまったのである。四二歳、日本では厄年にあたっている。
ビール好きとして有名なのは、アントンーブルックナー(一八二四~一八九六)である。
オルガユスト、長大な交響曲で知られるオーストリアの作曲家だが、彼は行きつけのビアー
ホールをもっていて、毎晩一時頃に現れると、ジョッキ二~三杯を平気で平らげたそう
である。ジョッキの大きさを想像してみると、もしかしてハリットル以上?大ビンー○本
は軽く超えていたかもしれない。食事もしたであろうから、その健啖ぶりにはまさに脱帽で
ある。しかし酒では死なずに、肺炎によって亡くなっている。
どの位の酒量かはっきりしないが、やはり酒好きだったと思われるのは、フランツー
シューベルト(一七九七~一八二八、オーストリア)、モーツァルト、ヨ(ネスーブラーム
ス(一八三三~一八九七、ドイツ)、ベートーヴェンらである。シューベルトは一五六セン
チぐらいという小柄な体格をしていたが、あだ名は。ビヤ樽气というのも仕事は午前中に
済ませて、午後は大抵酒場かレストランでどルを飲みながら友人たちと喋っていた。つまりかなりのどル好き(ただし、金のない時はそれより安いプンシュ酒)で、そのためにビール腹になったと思われるからである。
一方、モーツァルトも「銀の蛇」という行きつけのビヤーホールを、ベートーヴェンも
「駱駝」という飲み屋を行きつけにしていたと伝えられている。ベートーヴェンのそれは主
としてワインで、平常は赤、時にハンガリー産の白だったとか。客といっしよの時はビール
も飲んだという。しかし飲み過ぎることはなく、あくまでも食事をうまくするための健康的
な飲み方であったらしい。もう一人のブラームスはウイスキーで、これは何かの折にグラス
からこぼれたものを、「勿体ない」といって人前で平気でなめた、という話が残っている。
肝臓ガンで亡くなったことを考えると、かなりのドリンカーだったのかもしれない。食いしんぽうの作曲家
食べることは、人間のもつ根源的な欲望である。音楽家とて例外ではなく、これにこだ
わった人は大ぜいいそうな気がするが、音楽史に有名な食いしんぼう(食通といったほうが
よさそうだ)というと、まず思い浮かぶのは、イタリアの作曲家ジョアッキーノーロツシー
ニ(一七九二~一八六八)である。「セビーリヤの理髪師」「ウィリアムーテル」などのオペラで知られる彼は、七六歳の生涯のほぼ半分、三七歳の時に発表したオペラ「ウィリアムーテル」を最後に、ぷつりとオペ
ラ作曲の筆を折ってしまう。そして残りの大半は、それまでのオペラ(四作)から得た莫
大な収入をもとにパリに住み、旅や美食に明け暮れるといううらやましい生活を送ったが、
もともと食べることに関心があったせいであろうか。あれこれと食通らしいエピソードを残
しているのである。例えば、ある家の食事に招待されたが満腹しなかったために、帰り際に「また、お食事に
どうぞ」といわれて「今でもいいのですが…」と答えたとか、スパゲッティやマカロニの
材料に詳しく、パリのパスターショップの主人が出した偽の材料を見破って舌を巻かせた、
といった話は比較的よく知られたもの。もっとポピュラーなのは、現在でも高級レストラン
などのメニューに見かける「トウルヌドー・ロッシーニ」を残したことである。
ステーキの一種であるこの料理は、牛のヒレ肉を脂身で包み、糸で縛って円筒形にしたも
のを分厚く輪切りにしてバターで焼いたもの。これに鴨などのレバーでつくったパテを塗
り、野菜などを添えた上にマディラーソースをかけるという、いかにも脂ぎって太りそうな
代物。しかし、おいしいことは間違いなく、フランス料理のメニューには堂々と入ってい
る。毎日かどうかは知らないが、こういう料理を好んで食べていたせいに違いない。残され
ているロッシーニのスケッチや写真を見ると、いづれもでっぷりと太った、いかにも「食いしんぼう」そのものといった顔姿ばかりである。肉のロッシーニに対し、魚料理が好きだったのはベートーヴェンである。(イリゲンシュ
タットに住んだ時には、「薔薇亭」という料亭へよく魚料理を食べに行くのが習慣だったと
伝えられるし、客をもてなす時には、鱸(すずき)、鱈(たら)、鯉などの料理を好んで出し
た。それも良質なものをと、かなり神経質に手配したことが明らかにされている。
もっとも魚だけでなく、肉のシチュー、豚の血を固めた(ンガリー風のソーセージ、野鴨
その他の鳥肉の料理なども好きで、特にシチューの中にパンを煮こんだスープは大好物だっ
たという。ただ、自分で料理することはなく、大抵は家政婦にやらせていたようである。
そのほか、肉屋の息子だったドヴォルザークや、居酒屋に生まれたヴェルディなども、多
分、食べものには興味があったと思われるが、特にそれらしいエピソードは見かけない。た
だ戦前のわが国では確か「ヴェルディ風ステーキ」というのがレストランのメニューにあっ
た。何らかの裏話があるのかもしれない。
なお、作曲家ではないが、往年のロシアの名バス歌手フェオドルーシヤリアピン(一八七
三~一九三八)は、一九三六年に来日した折、帝国ホテルで「シヤリアピンーステーキ」と
いうのを作らせ、同じくソプラノ歌手N・メルバ(一八六一~一九三一、オーストラリア)
は、アイスクリームの上に桃などをのせたデザート菓子「ピーチーメルバ」を流行らせて、現在に伝えている。やはり相当の食いしんぼうだったに違いない。
変わった死に方をした作曲家
生まれたからには、だれにもいつかはやってくる死。しかしその形は、誕生の時に比
べて何と複雑で変化に富んだものであろうある人は若くして亡くなり、ある人は
歳を超えて枯木のごとく静かに朽ちる。長い病気に苦しんで逝く人がいれば、事故により一
瞬に消える人がおり、空に死ぬ人がいれば、海に没して見えなくなる人もいる。その多彩さ
は、さながら万華鏡をのぞくかのようである。
音楽家たちの世界も、また同じ。彼らの最後を見わたすと、病気による死はもちろん、ふ
しぎなきっかけによるもの、不運なもの、まさかと思うような原因によるものなど、いろい
ろな死に方をした人がいて、残された作品への興味をそそられることが多い。どんな死に方
をした人がいたか。特に変った死に方をした人について、この項でまとめてご紹介してみよう。
まず、まさか?と思うようなふしぎな原因で亡くなったのは、バロック時代のフランス
の作曲家ジャン=バティストーリュリ(一六三二~一六八七)である。なんと彼は、指
揮棒によって殺されているのである。オーケストラの指揮者が使う、あの指揮棒(タクト)のことだが、現在使われているものしか知らない私たちは、そういわれてもピンとこない。
じつはリュリの時代には杖のように長い棒を使い、拍子に合わせてドンドンと床を叩いて合
図していたのである。ある時、曲がクライマックスに達すると、彼は感情をこめて思いっき
り強く床を叩いた。と、それが床でなく、リュリの右足の親指だったからたまらない。激痛
と共に指は見る間に腫れあがり、やがてそこから入ったバイ菌に犯された彼は、あっけなく
死んでしまったのであった。
もっと不運なのは、第二次大戦が終わった一九四五年に、オーストリア近郊の小村で亡く
なったアントンーウェーベルン(一八八三~一九四五、オーストリア)だろう。彼は、たま
たま娘婿から貰った闇タバコを吸おうと外へ出て火をつけた瞬間、娘婿を見張っていたアメ
リカの憲兵の勘違いにより、射殺されてしまったからである。戦争が終わり。かつての日本
のように、オーストリアにもアメリカ軍が駐留して、彼らの物資を横流しする人たちを監視
していたのである。戦争がらみの不運といえば、スペイン近代のエンリケーグラナドス(一八六七~一九一
六)も同じ。彼は一九一六年の一月に、オペラ「ゴイエスカス」の初演をニューヨークで行
なった帰途、乗っていた客船がイギリス海峡でドイツの潜水艦に攻撃されて、夫婦で海に消
えているのである。第一次世界大戦が始まっていたのであった。そのほか、身の安全をは
かろうとして入った政党が革命で倒され、首を刎ねられてしまったエーデルマン(一七四九
~一七九四、ドイツ)。交通事故で亡くなったショーソン(一八五五~一八九九、フラン
ス)、フランク(一八二二~一八九、フランス)、ラヴェル(一八七五~一九三七、フラン
ス)の三人。自殺をしたワーロック(一八九四~一九三、イギリス)、クラーク(一六七
三~一七七、イギリス)、チャイコフスキー(一八四~一八九三、ロシア)。狂死した
シューマン(一八一○~一八五六、ドイツ)、スメタナ(一八二四~一八八四、チェコ)。葬儀用の音楽を作曲中に亡く
なったモーツァルト(いずれも詳しくは、拙著『作曲家とっておきの話』音楽之友社刊を参
照)…など、作曲家たちの最後も結構バラエティに富んでいることに驚かされるのでは
なかろうか。